きらり。9号の「障がいを知ろう」コーナーでは、児童期 、思春期 の発達障害 を特集しています。
現れやすい特性、家族ができる対応、自分でできる対応を具体的にお伝えしています。
また、
学校生活が始まると現れやすくなる 二次障害 の説明や、いじめ 、不登校 のことも特集しています。
家族だけでは解決しにくい問題がでてきやすいので
どうほかの支援機関と協力していくか、が大切になってきます。
支援機関も1つではありません。
専門機関のほかに、NPOや自助活動などにも頼りながら進めていくことで、
解決の糸口が見つかりやすくなります。
わたし自身も
小学生の時にいじめを体験、
鬱になってからは引きこもり期間もあります。
体験したからこそ、できることがあります。
#不登校支援 を家庭教師として行ったり
#カウンセリング をしたり
#学習支援 をしたり、
関わり方にはさまざまな方法があります。
この時期に親がしてしまいがちなことは、
成績、学習の遅ればかりに注目してしまいがちになること。
発達障害の子どもたちは、定型に比べると成長がゆっくりです。
精神年齢は、実年齢の3分の2、とも言われています。
子どもの心の成長やケアをまずは第1にすることが、二次障害や不登校の予防になります。
#学習 の遅れは、ゆっくりでも大丈夫。
ちゃんと追いつける年齢がやってきます。
焦りすぎないで、年齢に合わせながら進んでいきましょう。
当事者として言えることは
#二次障害 になったら、もっともっと大変だということ。
本人もですが、家族もとても辛い思いをします。
なにごとも、予防が大切。
心のケア、
一人で、ではなく、みんなでしていきたいですね。
ご注文はこちらから
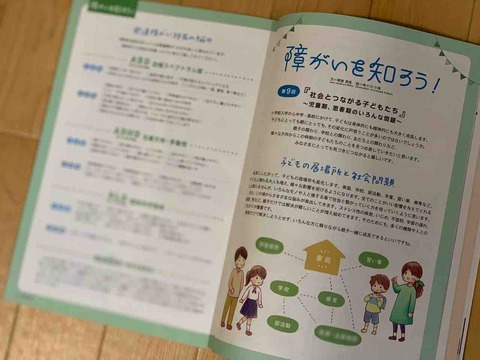





コメント